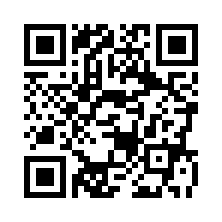
日向見薬師堂
永延3年(989)年のころ、源頼光の家来、碓氷貞光(うすいのさだみつ)が、越後から木の根峠を越えて日向見で夜を明かすことにして、谷川の音に心を静めて一晩中お経を読んでいました。
夢の中に現れた一人の童子から、「あなたの読経の真心に感心し四万(よんまん)の病気を治す温泉を与えよう、われはこの山神である。」と神のお告げを聞き、目を覚ますと、枕元に温泉が湧き出ていたという伝説があります。
このお告げをめでたいしるしと感じ、お堂を建てて本尊の薬師如来の像をまつりました。
この薬師様は病気を治す為に、温泉に来る人から「湯前薬師」と敬われ、昔から沢山のお参りがありました。
現在の堂は慶長3年(1598年)に、当時の領主「真田信幸(信之)」の武運長久を祈願して建立されました。また、天井に描かれた龍は複数の小さな足があり、
一説では「ムカデ」から想像されたとされています。
ムカデは武神である毘沙門天の使いであるうえ、前進しかせず不退転として武将に好まれていました。明治45年(1912年)に国宝に指定されましたが、昭和25年(1950年)の法律改正によって、国指定重要文化財となりました。県内最古の木造建築でもあり、関東地方では数少ない貴重な建物です。現在、薬師堂にはしゃもじが奉納されていますが、これは「救われる」という意味と、「食べる物に困らない」という願いが込められています。

